R4~R6の国土交通白書の課題を整理してみました。課題を整理して、現在主要な課題をまとめました。
令和4年 国土交通白書の課題整理
【働き方の観点】
- 近年、外気温が上昇している。将来的には昼間は熱中症を気にして屋外で働けない労働生産性や経済損失が課題。
- 未だに新型コロナウィルス感染のリスクが潜んでいる。インフラ分野においては、公共工事の現場で非接触・リモート型の働き方への転換を図るなど、感染症リスクに対しても強靱な経済構造の構築を加速することが喫緊の課題。
【担い手の観点】
- 建設業の現場では担い手の高齢化が進んでおり、将来的な担い手の確保が課題。
【高齢化社会の観点】
- 我が国では、65歳以上の単独世帯が増加傾向にあり、今後も増加すると推計されている。そのため、高齢者の避難の遅れなどが課題。
- 地域住民にとって必要不可欠な乗合バス等の生活交通確保・維持は、重要な課題。
【環境負荷の観点】
- 市街地の拡散は、社会経済の観点に加え、環境負荷の軽減の観点からも課題。
【災害の観点】
- 東日本大震災から11年を迎えた今でも、被災者が未だに不自由な生活を強いられている状況となっている。復旧・復興事業の推進が課題。
【リサイクルの観点】
- 建設副産物の再資源化に取組むため、①建設副産物の高い再資源化率の維持等、循環型社会形成へのさらなる貢献、②社会資本の維持管理・更新時代到来への配慮、③建設リサイクル分野における生産性向上に資する対応等が課題。
令和5年 国土交通白書の課題整理
【人口減少による地域の足の衰退や担い手不足の観点】
- 地域の足を支える乗合バスの現状は、輸送人員の減少、収支の悪化といった厳しい状況にある。このままの状況が続けば、暮らしを支える生活サービス提供機能の低下・喪失が生じる。そのため、地域の足の確保が課題。
- 建設業では、就業者の高齢化が進行している。今後は高齢者の大量離職が見込まれることから、建設業の魅力向上を図り、若年層の入職促進を含めた担い手確保が課題。
- 地域活性化を図るため、日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保が課題。
【働き方の観点】
- 我が国の労働生産性(全産業平均)は、2002年以降増加傾向にある。一方、建設業の労働生産性は、全産業平均より低い水準で推移している。そのため、労働生産性の向上を図ることが課題。
【都市計画の観点】
- 都市規模が大きいほど公共交通の利便性に対する満足度は高い一方、混雑緩和が課題。
- 都市部では、地震時等に著しく危険な密集市街地が集中している。都市部居住者の高齢化に伴い、今後、地域防災力が低下することも懸念される中、防災公園や周辺市街地の整備改善などのハード対策に加え、ソフト対策なども含めたまちづくり全体での対策が課題。
- 都市の再生において、官民が連携して市街地の整備を強力に推進し、海外から企業・人等を呼び込むことができるような魅力ある都市拠点を形成することが課題。
【気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化の観点】
- 2019年度の氾濫危険水位を超過した河川数は403件と、2014年度と比べて約5倍に増加している。人口の約3割が65歳以上の高齢社会である中、安全・迅速な避難への対策が課題。
- 防災対応については、一人ひとりが主体的に行動することが必要である。そのために、デジタル化の効果的な活用促進を図ることが課題。
- 災害が激甚化・頻発化しており、今後、気候変動に伴い災害リスクが更に高まっていくことが懸念される。そのため、ハード・ソフト一体となった防災・減災対策により、国民の生命・財産を守ることが課題。
【脱炭素化の観点】
- 日本は、2030年度に温室効果ガス46%削減(2013年度比)や2050年カーボンニュートラルの実現を目指し取組みを加速化している。取組みの一つとして、消費エネルギーの削減を図ることが課題。
- 気候変動の影響により、自然災害が激甚化・ 頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的な課題。
【維持管理の観点】
- 公共インフラの老朽化が進行しており、インフラメンテナンスにおいては、技術的知見を持つ人材不足やメンテナンス費用の継続的な確保が必要とされている。近年、予防保全に向けた取組みも求められている中、AIを取り入れて効率化・高度化を図ることが課題。
- 持続的・効率的なインフラメンテナンスを推進する必要があるが、小規模な地方公共団体において、体制面・予算面が課題。
令和6年 国土交通白書の課題整理
【地域の足の確保や担い手不足の観点】
- 長期的に労働投入量が総体として減少し、労働市場における担い手不足が課題。
- 建設業では、他産業を上回る高齢化が進んでおり、近い将来、高齢者の大量離職による担い手の減少が見込まれることから、中長期的な担い手の確保・育成が課題。
【災害の激甚化・頻発化の観点】
- 2024年1月1日に能登半島沖地震が発生しており、地震リスクが高まっているため、突発的な地震の対応が課題。
【高齢化社会の観点】
- 生活サービス施設へのアクセスとして、公共交通は欠くことができない移動手段であり、高齢者を含めた交通弱者に対する移動手段の確保が課題。
【維持管理の観点】
- インフラに不具合が生じてから対策を行う「事後保全」から、不具合が生じる前に対策を行う「予防保全」へ転換するなどしている。一方、適切な維持管理が求められる中、多くのインフラを管理する地方公共団体においては、財政面・体制面からインフラ老朽化への対応が課題。
【働き方の観点】
- 人口減少の深刻化等の課題への対応と併せ、多様な暮 らし方・働き方を支える持続可能で人間中心のコンパク トなまちづくりの実現に向けて、両計画の連携の強化を 図りつつ、都市中心部だけでなく、日常生活を営む身近 なエリアにも必要な機能が確保された地域生活拠点を形 成し、魅力向上を図ることが重要である。
【都市計画の観点】
- 海外から企業・人等を呼び込むことができるような魅力ある都市拠点を形成することが、課題。
- 高度成長期等において大都市圏の郊外部を中心に計画的に開発された大規模な住宅市街 地(ニュータウン)がある。ニュータウンでは、急速な高齢化及び人口減少の進展により地域の活力が低下している。そのため、ニュータウンの再生が課題。
- 他産業を上回る高齢化が進行する建設業にとって将来の担い手確保が必要である。そのため、多様な人材が入職し、かつ、働き続けられる業界づくりが課題。
使えそうな数値
令和6年度の論文に使えそうな数値をピックアップしました。良ければ参考にしてください。
- 日本は2070年には、人口が9,000万人を割り込むと推計されている。
- 高齢化も進行し、2070年には65歳以上が38.7%となると推計されている。
- 2023年時点における建設業の年齢構成は、55%が36.6%、29歳以下は11.6%となっている。
- 女性の就業者数は年々増加している。かつ、2023年10月末時点の外国人労働者数は約205万人と、2008年以降過去最高となった。
- 2023年の出生数は約73万人と8年連続で減少している。
- 高齢化率が40%を超える都道府県は、2050年には25の道県に増加すると推計されている。
- 2045年以降は、東京都を含むすべての都道府県で人口が減少すると推計されている。人口減少に応じた暮らした社会を支える取り組みが必要。
- 地域鉄道、路線バス共に、輸送人員は減少傾向にあり、約9割が赤字事業者となっている。
- 空き家の総数は、この30年間で、448万戸から900万戸へと約2倍に増加している。
- 日本の労働生産性は、「労働生産性の国際比較2023」によると、主要先進7か国では最下位となっている。
- 2016年度からi-Constructionに取り組んでいる。現在、土工では3割以上の作業時間削減の効果が確認されている。
まとめ
過去3年間の白書の流れを見ると、以下のテーマが課題となっています。2025年は択一になる可能性もあります。しかし、論文が継続される場合は、白書の観点からは、これらのテーマから出題されるかもしれません。
- 担い手確保
- 環境負荷低減
- 災害(特に、8月8日に日向灘で南海トラフ沿いに地震が発生したので、大規模地震について)
- 維持管理
- 地域活性化
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
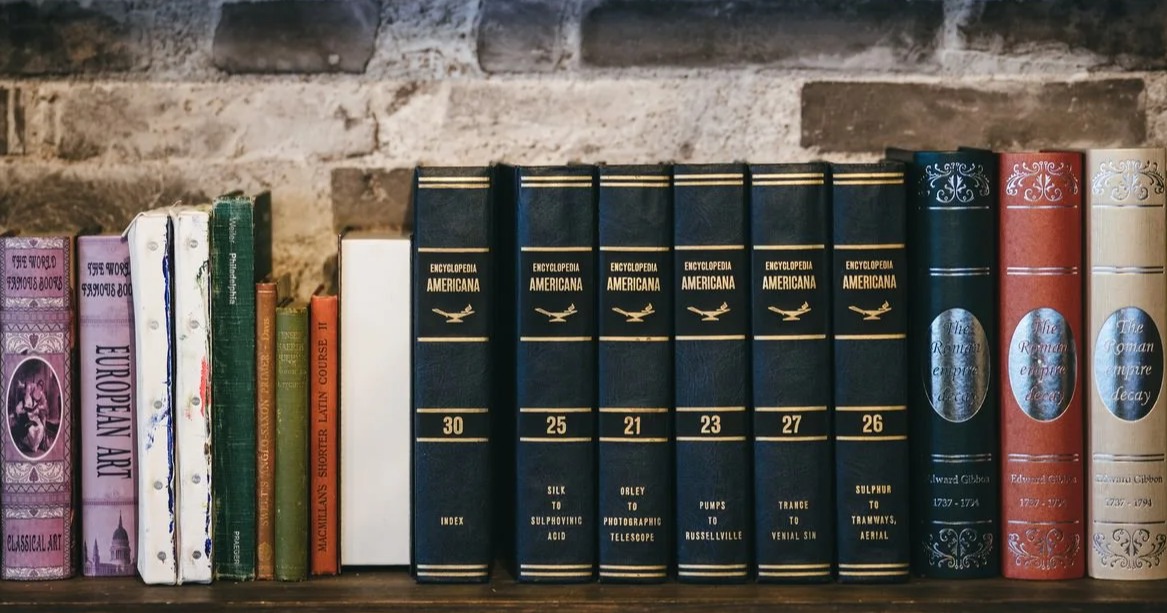


コメント